「侘び・寂び」は、戦国時代〜安土桃山時代を生きた茶人、千利休(1522~1591年)によって普及した考え方です。織田信長と豊臣秀吉に仕えました。晩年、茶人としての名声が高まるも、秀吉の逆鱗に触れたことで切腹を命じられ、70歳でその生涯を終えました。
「侘び・寂び」とは、質素なもの美を捉えるものの見方です。戦国時代末期、疫病や天災、飢餓など、明日の見えない暮らしの中で、茶道家や茶人が広めた考え方です。権力者の見るからに豪華絢爛なあり方に対するアンチテーゼの側面があります。アップル創業者・スティーブ・ジョブズ氏の影響で世界的に有名になった瞑想と同様に「侘び・寂び」も禅宗から派生した考え方です。
千利休が提唱した「侘び・寂び」の考え方と「銘木」は共通する部分があると感じています。この点について少し考えたいと思います。
侘び・寂び
「侘び」は一見するとマイナスに見える不完全なものに、「寂び」は時間の経過で変化するものに焦点を当て、それらに美しさを捉える考え方です。
侘びは英語では「incomplete(不完全)」、寂びは「impermanent(変化)」と翻訳されます。
不完全ないびつさや経年変化に美しさを捉える考え方です。日本の重要な美意識の一つです。
銘木に垣間見える侘び・寂び
銘木と侘び寂びは、不完全さや経年変化を前向きに捉えようとする点が共通しています。
時間の経過が形作る樹木の歪な造形や巨木の木目模様の美しさを評価して銘木と呼ばれます。この歪な形や美しい木目に着目し、造形に極端に振った場合、侘び寂びとは対極の豪華絢爛なニュアンスが強まります。
一方で、その成り立ちに着目した場合、侘び寂びに近いニュアンスになります。
銘木は侘び寂びと豪華絢爛の二面性を持っているということができそうです。
銘木のこれから
SDGSが謳われる社会の中で、巨木の豪華さにだけ着目したものづくりは時代にそぐわなくなってきました。銘木の力強い造形を押し出しただけのデザインでは人の心は動かなくなってきたのかもしれません。
一方で銘木にはその成り立ちとして侘びや寂びの要素が含まれています。侘びや寂びは豪華絢爛とは対局の考え方なのに、豪華絢爛をまとう銘木の成り立ちには詫びと寂びの感覚と似た部分があります。同じ素材のどこに着目するのかによって、出来上がるものも変わってくるのだと思います。
これは一つの捉え方に過ぎませんが、このようにこれまでとは異なった切り口から銘木を見てみることで、新たな発見があるのだと思っています。


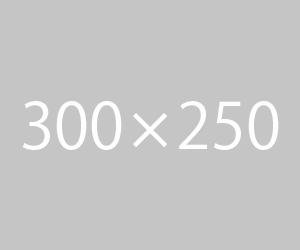



コメント